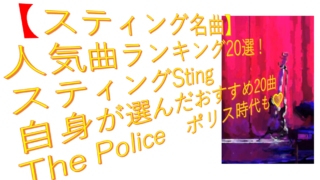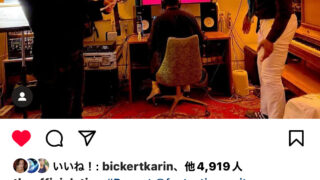みなさん、Wallace Delois Wattles
をご存知ですか。
ウォレス・ディー・ワトルズと訳されますが、
『富を引き寄せる科学的法則(The Science of Getting Rich)』
を書いた、超有名な作家さん。
1860年にアメリカにうまれ、南北戦争の時に生をうけ、
彼自身も貧困を体験し、そして学び
実践し、この
法則を見出して、本にしたというすごい人のすごい本。
1911年にお亡くなりになりましたが、
本当に多くの、特にアメリカでは非常に
知名度が高い作家。
その名著は時を超え、国を超え、
今でも、何か国語にも訳されて
多くの人に読まれています。
スティングの永久禁止と何が関係が?って
大ありなんです・・
もう少しガマンして読んでくれると
ウレシイ!💛 そう、永久禁止騒ぎは事実!
- あの10億越えを2025年に永久禁止とするのは 藝術の冒涜?と私は断固として主張します!!
- 30分で書いたのは、インスピレーション!神の手? ボブプロクターも愛したScience of Getting Rich
- “見つめていたい” は、ストーカーだ! だから禁止!は?代わりの曲は…
- イギリスの芸術教育とは??
- ステンイグのEvery Breath You Takeの代わりが ”Learn To Fly “飛ぶことを学ぶ?…は?
あの10億越えを2025年に永久禁止とするのは 藝術の冒涜?と私は断固として主張します!!
この、”The Science Of Grow Rich “の
本の中にこういう一節があります。
“<唯一の実体>である神は、
私たち人間を通してこの地上に生き、
多くのことを行い、楽しもうとしています。
神は次のように言っています。”
原文P42; By Wallace D. Wattles 1910
God, the One Substance, is trying to live and do and enjoy things through humanity. He is saying “I want hands to build wonderful structures, to play divine harmonies, to paint glorious pictures; I want feet to run my errands, eyes to see my beauties, tongues to tell mighty truths and to sing marvelous songs,” and so on
「私は立派な建物を建て、美しい音楽を演奏し
素晴らしい絵画を描くための手が欲しい。
私の仕事をするための足を、
美しい自然を見るための目を、
力強い真実を述べ、素晴らしい歌を歌うための
のどが欲しい」と言っています。
すべての可能性が、人間を通して
表現されることを求めています。
神は音楽ができる人にはピアノやその他の
必要な楽器を手に入れてもらい、
彼らの才能を最大限に伸ばすことを
望んでいます。
美の価値のわかる人には、
美しいものを身の回りに置くことを
お望みです。
真実がわかる人には、機械あるごとに
旅をして健をして見聞をひろめることを
求めています。
Page39
音楽を演奏したいという欲求は、
表現と発展を求めている力のしるしです。
Page.81
全てを知っている<神の心>があります。
あなたが深く感謝するとき、信仰と前進しよう
という決意によって、あなたはこの<神の心>
と一つに通い合う事ができるのです。
Page.83
原題:The Science of Getting Rich
角川文庫出版
富を「引き寄せる」科学的法則
ウォレス・ワトルズ;訳 山川紘矢・亜希子
私がこの本を思い出したたのです。
Rock Choir: ロック・クワイアの永久禁止をきいて・・
ピンと来られた方いらっしゃいますか?
2025年にもなって、まだ芸術に
人の枠をはめようとする・・SNSの制限禁止とおなじようなもの・・
そこには大きな犠牲を払うことになる・・
30分で書いたのは、インスピレーション!神の手? ボブプロクターも愛したScience of Getting Rich
「夜中に目が覚めて、頭の中にあの一節が思い浮かんだ。
”君の息づかいも、行動もすべて、僕は見ているよ
(Every breath you take, every move you make,
I’ll be watching you)”」1993年のインタビューで
スティングはこのように回想している。
「ピアノの前に座って、30分で曲を書き上げたんだ」。
Udiscovermusic.jp より引用↓下記に詳細
https://www.udiscovermusic.jp/stories/every-breath-you-take-sting-police-song
これって、まさしく、
神がスティングの才能を通して、
音楽を表現したかった!
そこで、今日電車の中で、
ある記事を読んで、は?!と
感じずにはいられなかった、というわけです。
「イギリス全体で31000人以上の参加者がいるRock Choir: ロック・クワイアは
長年にわたって“Every Breath You Take”を歌唱してきたが、
今回レパートリーから外されることが明らかになっている」
Full Story👉
NME JAPAN:https://nme-jp.com/news/151697/
え、なぜ?て思いませんか?
芸術の解釈に限定をかけてそれを禁止する?いま2024年です!
っていいたくなりませんか?
そしてこの執筆をしてるのは2025年。
撤回の兆し全くなし!
あんなに、あったかい、まるで神のような愛!
いつも見つめていたい!とも解釈できるすばらしい楽曲を・・
そうそれで、調べました!
このRock Choir: ロック・クワイアの決定理由を?
“見つめていたい” は、ストーカーだ! だから禁止!は?代わりの曲は…
まず、代わりの曲から
疑問を呈する!
タイトルが、
”飛ぶことを学ぶ”?ハ?
そして、スティングの『見つめていたい』
原題: Every Breath You Take、を禁止する。
禁止理由が
歌詞の内容において、
主人公が恋愛対象をストーキングしていると
みられる迷惑行為が書かれている・・
マジっすか!
あのね・・・・・
じゃ、車の写真は、
人をひくことごできるから、見ない方がいいですか?
日本刀は人を切る武器だから見ない?
西洋のBow and arrow (弓矢)も
もともとは動物や人への武器として
人がつくったもの・・
藝術として見る場合があるでしょ!!
幼稚すぎて、開いた口がひらかない・・
中学生の委員会で協議されるような内容。
そこに芸術の先生がでてきて・・
音楽と芸術の先生が・・多分
こう未熟なものたちを諭すんじゃないでしょうか?
”芸術作品というのは、音楽であれ、
工芸品であれ、壁画であれ、
藝術作品の解釈は
多様であるものなんだ。
多様であっていい。
特定の解釈ができるから
という事を理由に作品の公開や
演奏を制限することは
藝術の多様性や、芸術の受け取る人の自由
そして選択の自由を阻害することにならないかい?
しかもこの曲 Every Breath You Takeは、
もう40年という時間が素晴らしさを実証しているじゃないか?
全然問題がないからこそ
そして 逆に人の心に癒しと愛をあたえてきているからこと
10億回ストリームになって
時代を超えた名曲として
愛されているんじゃないかい?
製作者の意図や一部の解釈に基づいて
作品を制限するということは、
”芸術” という本来の意味を阻害する可能性も
あるだろう。
創作するものと
それを観賞するものとの間に
1本のトンネルをつくって
今の場合だと、ストーカーのトンネルだ!
その1本の本当に小さいトンネルがあたかも
それからしか、人々が見れないかのように
理由をつけて、禁止し糾弾する
そんなおかしなことがあっていいものか?
それが理解できるかい?
人の心は複雑かつ、大いなる愛があり、
それを人生を通して育て学んでいく生き物だ。
様々な芸術はそれを助けてくれる。
スティングのこの「見つめていたい』は
創作者がどのような意図でその一瞬においてつくったとしても
作品は作品だ!
「ミロのヴィーナス」も君たち
勉強しただろう。
両腕が失われているため、
鑑賞者は彼女がどのようなポーズを取っていたのか、
それはわからない。
何を持っていたのかわからない。
つまりそれを想像する余地があるんだ。
それこそが芸術であり、心をそだて愛を育てる。
この「不完全さ」が逆に作品の魅力を高めているとの指摘も
あるくらいだ。ただそのミロのウィーナスを作った人が
どう考えてつくったか・・それはその創作者の自由であり
それを理由にして、「ミロのヴィーナス」を箱にいれてしまうのかい?
そしてそれをあたかも悪者のように糾弾する・・
そんな幼稚ともいえることってあるかい?!
作者は変なエロなことを考えていた可能性があるってね?
だから禁止だって!!
わかっただろう?どれだけ未熟な判断か・・
藝術の多様な受容を阻害する行為は
本当に本当に慎重に考慮されるべき問題だ。”
・・と芸術の先生が子供たちを戒め
導くレベルだと思います。
イギリスの芸術教育とは??
理由が未熟すぎて、
あいた口が閉じられませんでした。
じゃ、… 聖歌隊の曲は全部ストーカーか!!
いや、それは、作った動機が違う?
一緒だよ。
観賞するのは作った人でなく、
創られてモノを見る鑑賞者だ!
神様の曲は全部ストーカーの危険性があるってこと!
まあ、天罰っていう言葉があるくらいだから??
愛があれば、危害を加えないのは、
愛の表現じゃないのか?
ギャングがみるか神様が見るかを
Rock Choir: ロック・クワイア
の皆さんはお決めになるのですか?
監視しているのは、危害を加えるためとらえるか、
それとも、愛としてあたたかく見守るかは、
芸術を鑑賞するひと次第なんじゃないの?
ステンイグのEvery Breath You Takeの代わりが ”Learn To Fly “飛ぶことを学ぶ?…は?
それは、へんな薬物を摂取して、
飛ぶことを学ぶっていう解釈できるので、
超危険で禁止!っていえませんか!!
つくった人はそうおもっていなかった?
鑑賞者は作った人の気持ちをしってから、
枠にはめて聞くのですか?
どんな思いで作ったかは
100年後の芸術鑑賞者に
問題ですか?
あのね!動機は神様のインスピレーション!
10億回きいて、
誰か、危害を与えようとおもう、
行動に出たくなる曲ですか?
Rock Choir: ロック・クワイアの決定を下した人だけですよ!
レオナルド•ダ•ビンチが何を考え絵を描いていたか、 それは、その芸術家が最高のものを発揮するインスピレーションであり、 極度の集中から出るものなんじゃないですか? スティングも、芸術家として 最高の曲を発揮するインスピレーションから 創った・・となぜ理解できない????
俳優は映画で怒るシーンで何を考えていようと、
スクリーンですごい真にせまる演技であれば、
それは評価させるべきなんじやないのかなあ。
… もう、怒りとおりこして、 呆れてます。
2025年ですよー!
その芸術鑑賞の根本をなにか、履き違えてませんか?
世界を狭くしていませんか?
芸術を、コントロールして、正しい、正しくない、 と言い出したら、芸術が芸術でなくなってしまう。
私などは思います。
皆様は、どうですか?
これも、ある意味、最高すぎる、
ワンランク上の芸術作品だからこそ、
人類が通り、学ぶべきステップなのでしょうか。
かつて、スティングの『ロクサーヌ』が
BBCで放送禁止になったように。
ある意味、スティング、そしてポリス。
本当にすごい音楽を世界に提供してくれたんだなあ、
とあらためて感謝です。
ストーカーという概念はあたらしいかもしれないけど、それを芸術作品に適用しよっていう発想が、あまりにも芸術的に幼稚だと私は勝手に思いました。
皆様どうですか?
Rock Choir: ロック・クワイア は
何を考えてるのか。
Sting: スティングが73歳になっても、
止まること知らないので、ジャラシ〜?
嫌がらせ?
人間の、妬み、嫉み、恨みとまで言わないけど、
おかしいでしよ!
2025年だよ・・・
音楽は芸術の中の芸術!
芸術に棒線引きするのは、
言論の自由を奪うよりも恐ろしい。
心の中に手を突っ込もうとする行為。
しかも、ストーカーだと解釈できるからって、
そうすると、モナリザは怒っているように見える可能性があるから、
美術館からはずすっていうのと、
まったく同じ!
BBCが「ロクサーヌ」をかつて 禁止しました。
それは娼婦への愛・・だからとか・
【スティング名曲】48年以上売れ続ける秘密?『ロクサーヌ』という名の 娼婦への熱い愛❤最高傑作はかつてBBC放送禁止。歌詞和訳 “[Sting’s Hits] Bilingual Edition ★Sting mansion Live Recordings?”A Passionate Love for a Prostitute ❤ The Secret of the Greatest 37years Hit ‘Roxanne’ from 1977 Lyrics Translation & Background”・
人間が愛を理解するなかで、
21世紀になって少し成長してきたんじやないかとおもいます。
それで今では禁止がなくなった。
Rock Choir: ロック・クワイアも、
成長が必要ですねってことなんでしょうか。
10億回以上Spotifyで再生されたってことは、
人の心を癒しているんですよ!
これは間違いのない事実。
しかも10億回が証明するように、
本当に多くの人の心を、魂をハートを
愛でいっぱいにしている・・
さみしい・・そんな解釈をして禁止にする人たちが
まだ地球上にいるという事実が・・
********
ここからはおまけ・・
興味のある方だけ読んでくださると
うれしいです。
愛のお話
ロクサーヌで思い出したのが、 池袋のお寺!娼婦への愛!
日本でも実は大昔 事実として
同じようなことがあったんです・・
悲しい娼婦への愛
池袋の本立寺は愛の涙・・娼婦への愛
池袋の本立寺は、日蓮宗のお寺です。
姫路藩主、榊原家の奥方の菩提寺でした。
この本立寺(ほんりゅうじ)の境内にある。吉原の遊女6代目
高尾太夫(たかおだゆう)という女性のお墓があります。
この女性は姫路藩主の榊原政岑(さかきはら まさみね)
に溺愛されてしまう。

そして1800両で身請けされることになる。
といっても身請けって・・
「身請け(みうけ)」とは、
主に江戸時代の遊廓(ゆうかく)などにおいて、
遊女の身分を買い取って自由の身にするための行為でした。
遊女は多くの場合、借金や家族の事情などが理由で
遊廓(遊郭)に売られており、
契約期間がある間は基本的に
その場所で働かざるを得ませんでした。
かわいそうですよね‥
そこでお金落ちがお金を払って
自由の身にしてあげることを
いうんですね。
多くの場合は、
お金をはらってもらったので
その方と結婚したり、
別の職業という場合もあったそうです。
ところが・・・
それを聴いた当時の将軍、徳川吉宗!
怒ってしまったんです!
(古い!)まあ江戸時代!(笑)
愛に正義という名の
鉄拳を・・なぜ・・と
私は思ってしまう。
愛は愛・・・だれがだれを愛そうと愛
なぜ そこに線引きをしてしまうのか・・
そしてその姫路藩主は強制隠居、
まあ今で言うと退職って感じでしょうか
そして、榊原家も転封(てんぽう)といって、
国替(くにかえ)、
いまでいうと左遷のような処分を受けたんです。
姫路藩主の榊原政岑(さかきはら まさみね)と、
高尾太夫(たかおだゆう)という女性は
その転封(てんぽう)(=左遷のような処置)
に移り住みますが、
藩主は間もなく亡くなってしまいます。
心労・・ですよね。
愛に身を捧げ、愛で稼いだお金を使い
愛のためにそれをつかって
愛する女性を自由にした・・それで
社会的地位を失い・・周りの目もあったでしょう。
人はなぜ理解できない・・愛を・・
私は涙が出てしまい
心臓が苦しくなります。
そして高尾太夫(たかおだゆう)は出家し、
仏教の道へとはいります。
神に助けを・・もとめたのでしょうか。
愛をもとめ、愛を学ぶ・・愛に助けを求める
女性のお坊さん、尼(あま)になります。
姫路藩主の榊原政岑(さかきはら まさみね)の
「死後の幸福」や「成仏」を祈ったといいます。
そして、江戸に来て、当寺で余生を送ったそう。
愛の素晴らしさ・・
愛の苦しさ・・
愛の辛さ・・
そして愛の強さ・・・
心と魂でこみ上げてきませんか?
音楽という芸術でも感じる愛です。
ロクサーヌと通ずるところがありますよね。
そして わたしは言いたい!
「芸術の価値は、見る人の目、聞く人の耳
感じる心と魂によって決まる。」
芸術作品の解釈は、鑑賞者の視点によって異なります。
このことを表現するための洗練された表現として、
以下の日本語と英語のフレーズは超有名。
「芸術の価値は、見る人の目によって決まる。」 “The value of art lies in the eyes of the beholder.” ことわざ;Saying
この表現の意図するところを、
考慮しなかったのは、本当に不可解で残念。
芸術の評価は主観的であり、
各人の視点や感性によって
異なることはあまりにも周知の事実。
10億ストリームされ、聞けば心と魂に響くこの曲を
禁止する理由があまりにも浅はか・・・
藝術鑑賞者よっては、あたかも神のような あたたかい愛を万人に近い人が感じるから! だから10億回以上再生ストリーム!
芸術の解釈が個々の経験や価値観に大きく
依存しますが、今回の決定は本当に不可解。
このRock Choir: ロック・クワイア
の決定理由から、こうも言えませんか。
歌詞の内容において、
主人公が恋愛対象を神の愛としてみられるところがあり、
ストーキングしているとみられる
迷惑行為が書かれている。神からの迷惑行為😅
Rock Choirの創設者であるキャロライン・レッドマン・ラッシャー氏は、
メンバーからの懸念を受けて、この曲をレパートリーから外す決定を下しました。
代わりに、Foo Fightersの「Learn to Fly」が追加されました。
”一部のメンバーが不快感や懸念を示した” ため・・
大人の方が、不快感や懸念を示すというのは、
その人の心にそういうものがあり、
それを映し出しだしている可能性が大きい。
結婚式でこの Every Breath You Take
(邦題:”みつめていたい”)を聴いて
だれがストーカーと考えるのか?
芸術とは一つの学びとして
それをみて何を感じるか・・
そこから学び、成長するという意味合いも
ないっていったら、100%反対できますか?
また40年後ぐらいに見直されるのでしょうか。
音楽を軽くみすぎているのでは?
芸術です!
追伸:
ミロのビーナスやミケランジェロの『ダビデ像』は、
ルネサンス期の傑作として広く知られていますが、
不快に感じるひとがいないといえますか?
(2025年3月22日 執筆)